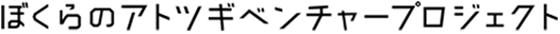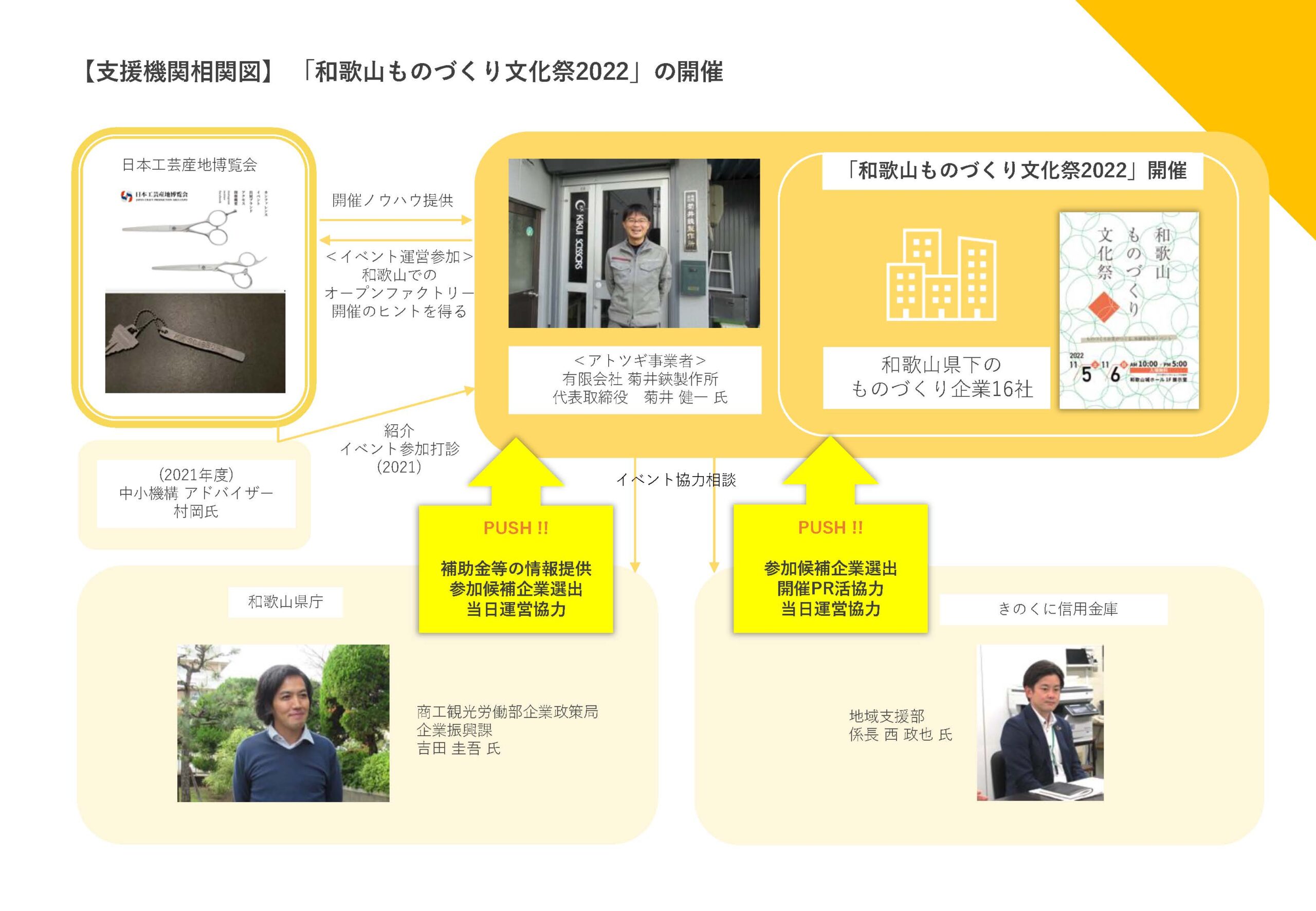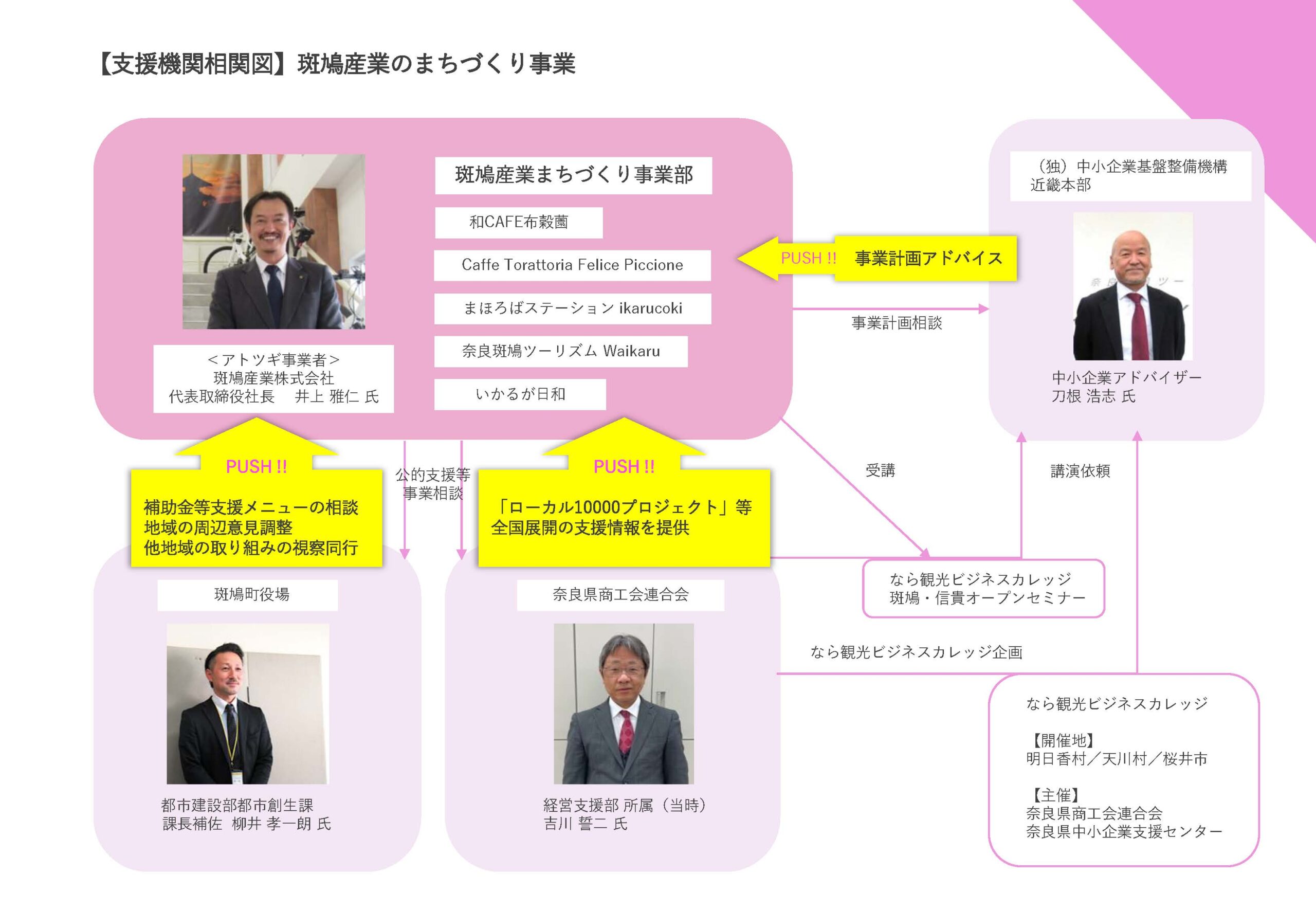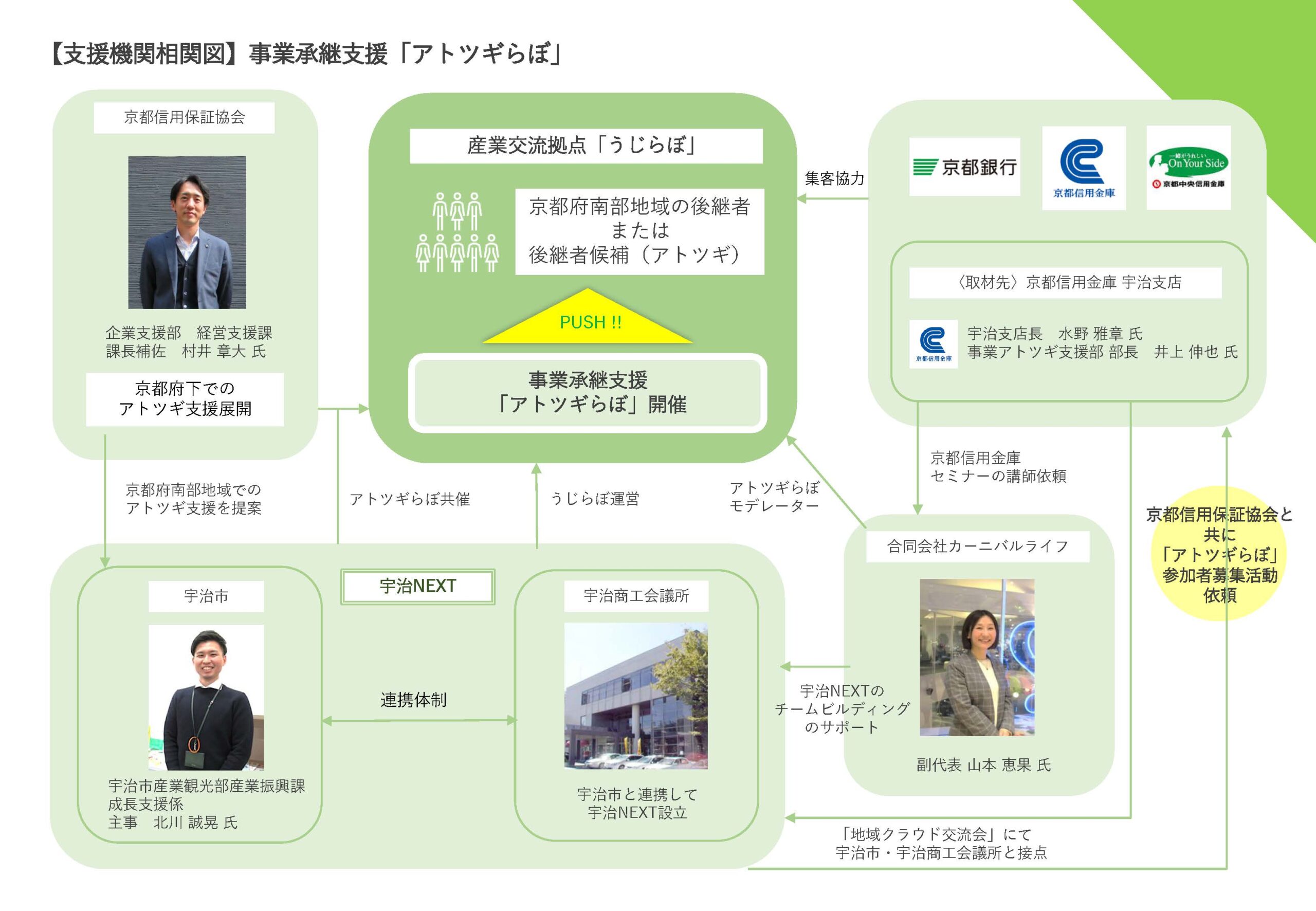2018.09.25
【インタビューVol.20】『お義父さんと働いてみたい』という思いから始まった、伝統工芸の世界での挑戦(株式会社ナカニ/中尾弘基氏)

大学卒業後、一般企業での勤務を経て義理の父が経営する会社ナカニに入社。手ぬぐいブランド「にじゆら」の販路拡大や、デザインから行う工場づくりなど、注染を広めるための活動に尽力している。
Q. ナカニはお義父さんの会社ということですが、なぜ継ぐことになったのでしょう?
A. 結婚することになったときに「継がへんか?」みたいな話になって
嫁とは大学生のころからの付き合いで、付き合ってすぐのころから実家にも遊びに行かせてもらっていたし、ビラ配りなどのお手伝いもしていたので、商売をやっているのはもちろん知っていました。
当時別の会社に勤めていましたし、嫁からも反対されていたので断ろうと思っていました。嫁は大学卒業後にすでに会社を手伝っていて、大変さを知っていたので巻き込みたくなかったみたいです。
そんなあるとき、高速で車が大破する大事故を起こしてしまったんです。奇跡的に無傷で済んだこともあり、「1度死んだようなものだし、やってみよう」と逆に気持ちが固まって。半年待ってもらって勤めていた会社を辞め、ナカニに入社。26歳のときでした。
その当時、会社は「にじゆら」が4年目で、これから拡大していこうというタイミングでもあり、人手不足などで厳しい状況でした。そこで、たまたまいた自分に白羽の矢が立った感じです(笑)

Q. 元々経営には興味があったのでしょうか?
A. 社長になりたいという気持ちはありましたが、実家が建設業をやっていて潰れてしまったこともあり、経営の大変さも知っていました
なので、会社にいながらサラリーマン社長みたいな感じがいいな、というくらいの気持ちで。でも人に指示されて動くのは好きではなかったので、自分が主体的に何かをやっていくのは向いていたのかもしれません。
そもそも、海外で働いた経験があれば社長になれるという思い込みがあって(笑)海外勤務のある一般企業に新卒で入社しました。
会社は海外拠点の現地社長を育成するような方針があったので、入社後すぐにドイツ、イタリアで勤務をしていました。経営的なことを色々と勉強させてもらったんですが、しばらくして会社の粉飾決算が発覚して。同時期に親の病気が重なったこともあり、関西に戻らせてもらったんです。今はもうその会社はないので、結果的に退職して良かったと思っています。
Q. 奥様のお義父さんが社長ということでやりにくさはなかったですか?
A. それは特になかったです。むしろお義父さんの人柄に惹かれて入社したんです
僕は実家の会社が潰れてから家も無くなり、両親も別れてしまいまして。正月も帰る家がなくて、結婚前からいつも嫁の実家に帰らせてもらっていました。
前職での粉飾決算に直面したときには、大人の汚い面をたくさん見て失望したのですが、お義父さんはそういう大人とは全然違って。キラキラしているし、楽しそうに仕事をしていたんです。「この人と一緒に働いてみたいな」「この人がやっていることをもっと知りたい」という気持ちがありました。
会社の人にもよくしてもらっていましたし、伝統工芸の世界は全く知らなかったので不安もありましたが、嫁やお義父さん、周りの人たちとの繋がりだけで入社した感じです。お義父さんとは今では喧嘩もしますけど、2人で出張に行ったりもします。実の息子じゃないから逆に良いのかもしれませんね。
Q. 入社されてからはどのように働かれたのでしょうか?
A. 社長からの仕事の指示は一切なくて、最初の1週間はひたすら手ぬぐいにアイロンを当てていました。「これじゃあかん!」と思って、営業部、企画部などの部署を作り、勝手に営業部長として動き始めたんです

写真提供:株式会社ナカニ
最初の1年は工場に見学のお客さんがたくさん来られるので、その対応をしながらひとつひとつ技術を勉強していった感じで。
「にじゆらの店舗以外で1億円を作る」を目標にやっていたのですが、転機は中川政七商店の前社長、中川さんからお誘いいただいたこと。展示会などに参加させていただいて、中川さんから工芸の世界のことを色々と教わりました。売り上げも伸びて知名度も上がりましたし、中川さん流の、「個別の営業をせずに展示会で売るスタイル」はとても勉強になりました。
Q. 他に工夫されたことはありますか?
A. 卸だけでは限界があるので、自分たちで1からものづくりができるようにしました

写真提供:株式会社ナカニ
手ぬぐいは単価が低いのでとにかく数を売らなければいけません。なので最初は各都道府県ににじゆらを扱ってもらえる場所を作ろうとしていたんです。
でもやっぱり卸だけでは限界があるので、自分たちで1からものづくりができるようにしました。
注染という技術は独特のものなので、工程がわかる人がデザインをしなければいけません。自社に染めを勉強していたデザイナーがいたので、ブランドマネージャーに抜擢し、デザインから自社で行うようにしました。その場で職人と話をしながらデザインを組めるので、すぐ形にできて、改良もできます。

写真提供:株式会社ナカニ
にじゆらの名前の由来でもある「滲みと揺らぎ」の染めができるのは、高い技術がある証。今はそれを理解して、にじゆらが好きで扱ってくれるお店にしか置かなくなりました。
うちは商品がてぬぐいだけなので、飽きられずに見せ続けるには変化をしていく必要があります。そういった意味で現場と企画が一体になってるのは大きいです。
そして、工場は職人だけでなく、デザイナーも育成することができる。日曜日には工場を解放していて、好きなデザインの型を作る職人もいます。そこから新たな商品が生まれることもあるし、工場があるのはやはり強みだと思っています。

Q. 1番苦労されたのはどういうところでしょうか?
A. 最初の2年くらいはただただ忙しくて。自分がやりたいことも見つけられていなかったので、やらされている感があって辛かったです
「これじゃあサラリーマンと変わらない!」と思っていたし、嫁とも喧嘩ばかりしていました。
でも入社3年目に、大阪駅にある商業施設「ルクア」に店舗を出させてもらってから意識が大きく変わりました。
東京にも店舗を出したばかりだったし、社長は大反対。でも、僕はどうしてもやりたくて、初めて大喧嘩したんです。
お互いの奥さんに止められるくらいの喧嘩になってしまって。しかも駅で!(笑)
最終的には社長が折れてくれて出店したのですが、そこから主体的に動けるようになって、やらされてる感のある辛さが抜けました。ルクアの中で他と競ることで色々と学べるし、小売業としての経験を積む上でもやるべきだと思っていて。今4年目ですが売り上げもよく、にじゆらが若い層にも届いたので本当に出店できて良かったです。
社長も今では逆に「ここにも出そう」なんて言ってきますよ(笑)。
Q. 今後の夢は何ですか?
A.「大阪のお土産といえばにじゆら」と言われるようにすることですね

写真提供:株式会社ナカニ
大阪はこれからさらに駅も増えるし、追い風だと思っています。店鋪も増やしていって、大阪発祥感を定着させたいですね。
あと、今「にじゆら」のブランド名だけが1人歩きしている感じですが、ナカニという染め工場のブランドだということを広めたいです。ナカニは「ものづくり企業」であって、てぬぐい屋ではない。注染でものづくりをしているんです。注染のことはナカニに相談してみよう、となるのが理想ですね。そのために他の商品展開も考えています。僕は染められない3代目なんですけど、注染を広めることが目的なので、そちらを頑張りたいなと。
注染という技術を残していくためなら、誰が社長になっても良いとさえ思っています。

注染:染料を注ぎ、染める技法。表からと裏からの2度染めることで裏表なく綺麗に染まるのが特徴。職人の手作業だからこそ表現できるぼかしや滲みの何とも言えない風合いが1番の魅力と言える。
(文:宇野真由子/写真:宇野真由子)
株式会社ナカニ
〒599-8266 大阪府堺市中区毛穴町338-6
http://nakani.co.jp/
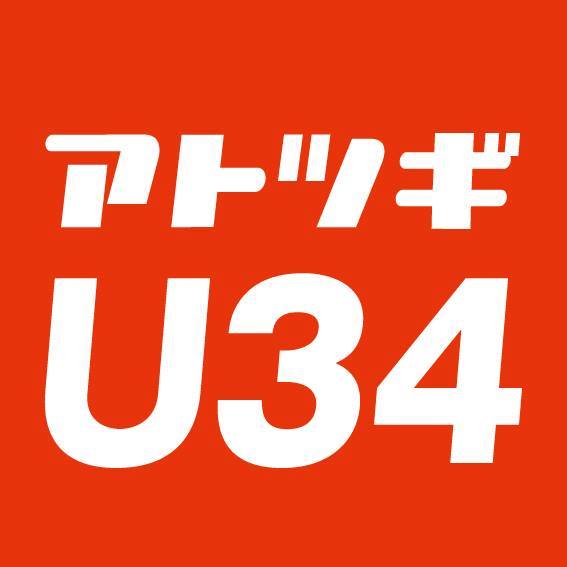
アトツギベンチャー編集部
おすすめ記事

2022.02.04
【インタビューvol.54】「違和感」は新規事業の原動力、時代の風を読んで取り組むフードロ
壷井氏は32歳で家業を継いで以降、社内外で「ただ課題解決のためだけ
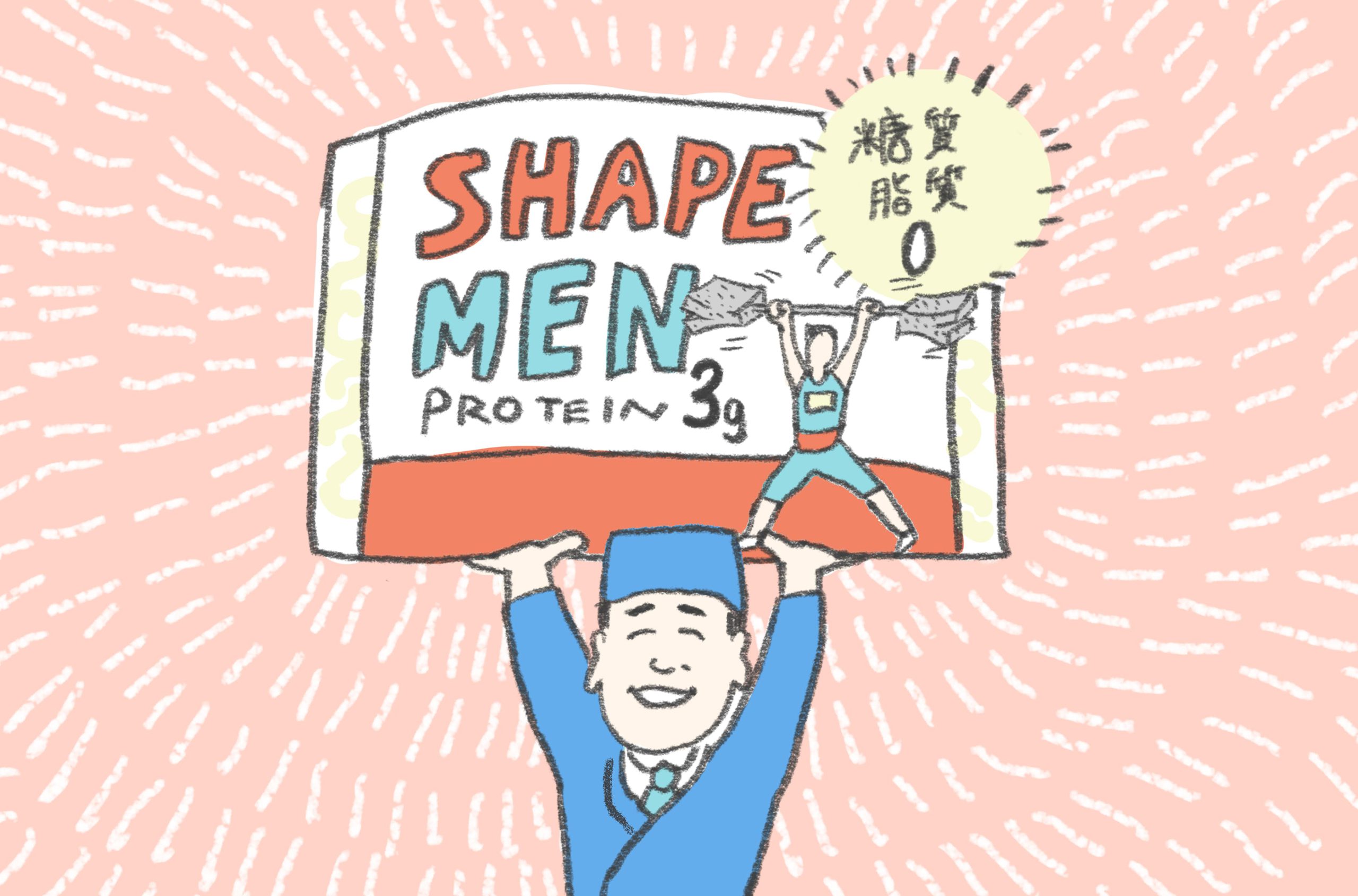
2022.01.26
【インタビューvol.53】ワールドワイドに広がれこんにゃく文化! 「SHAPE MEN」
Q. 「SHAPE MEN」って?? 一般的な「こんにゃく」とは違い、身体にじっ

2022.01.24
【インタビュー Vol.52】国内初、紙パックナチュラルウォーターで業界を革新(株式会社ハ
市販されている「水」といえば、容器は「ペットボトル」。それが当たり前だった日本で

2022.01.17
【インタビュー Vol.51】20歳で掲げた夢は「世界に必要とされる企業にする」。菓子卸売
全国に売店192店舗、食堂36店舗を展開している心幸ホールディング

2022.01.13
【インタビュー Vol.50】社員の1/3は虫博士。「個人が自立したフラットなチーム」と「
片山氏は35歳で家業を継いで以降、殺虫剤用の噴霧器メーカーから防虫資材商社へと業

2021.03.05
【アトツギピッチ優勝者インタビュー】 “船場”からテクノロジーの会社ができたらおもしろい!
2021年1月23日に開催されたアトツギピッチで優勝した株式会社志成販売の戦正典

2021.03.04
【インタビュー Vol.49】本当に美味しい生パスタを届けたい!麺一筋110余年のノウハウ
淡路島中北部の大阪湾を望む立地に本社兼工場がある淡路麺業株式会社。併設されている

2021.02.26
【インタビュー Vol.48】社長業は未来をつくる仕事。人を育てることを軸におき、家業の製
昭和11年にゴム材料商社として創業し、高度経済成長期を経て、ゴム製品を製造・販売

2021.02.24
【インタビュー Vol.47】農業×I Tで見えない技術資産を未来へつなぐ。(有限会社フク
「実は、家業に入ったきっかけはあまり前向きな理由ではなくて・・・」と苦笑しながら

2021.02.23
【インタビューvol.46】特殊曲面印刷の技術を導入する体制構築や、人材育成に注力。ライセ
福井県の特産品といえる眼鏡を販売する会社として創業した株式会社秀峰。ギフト事業参