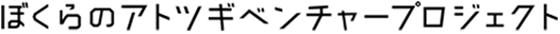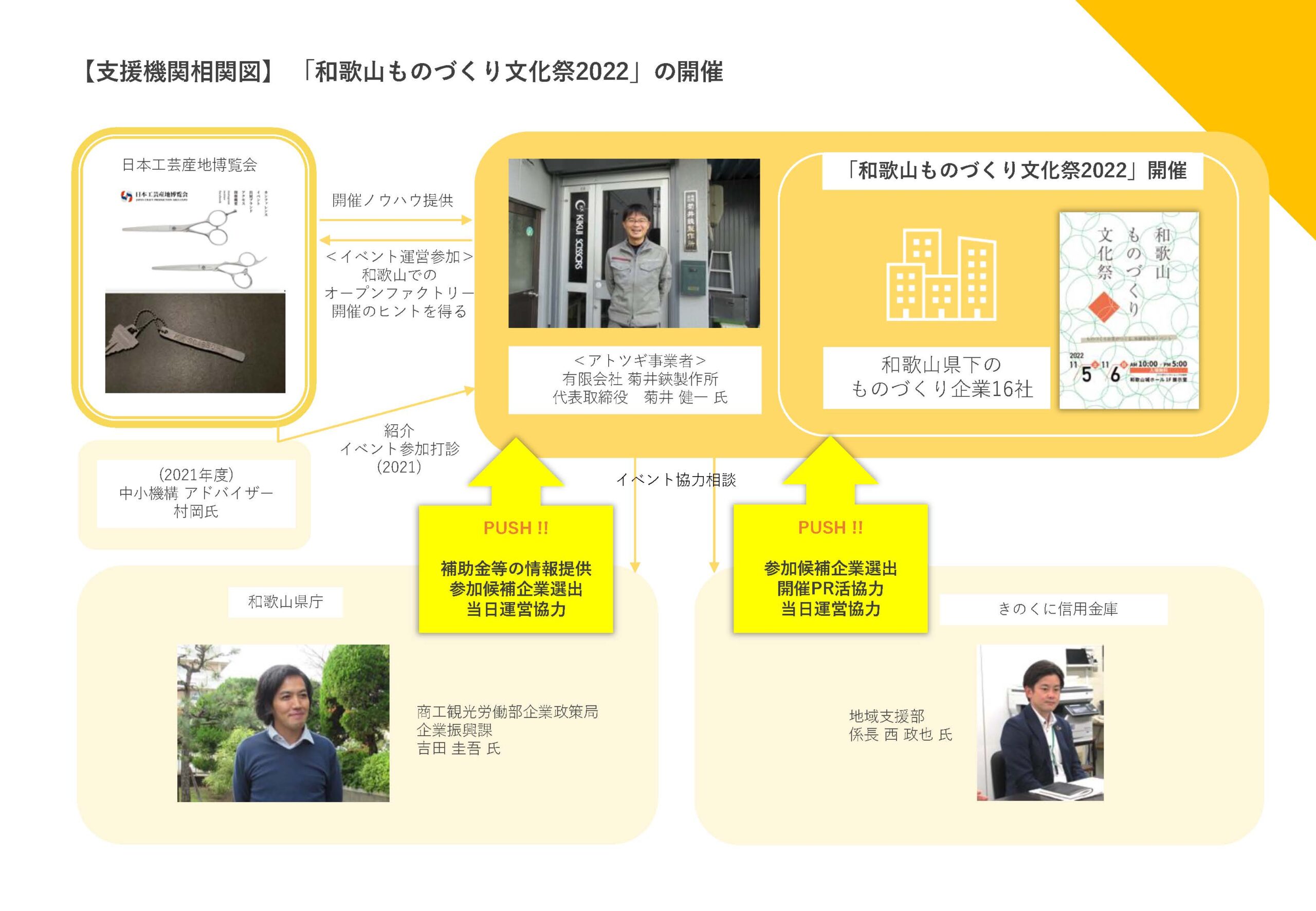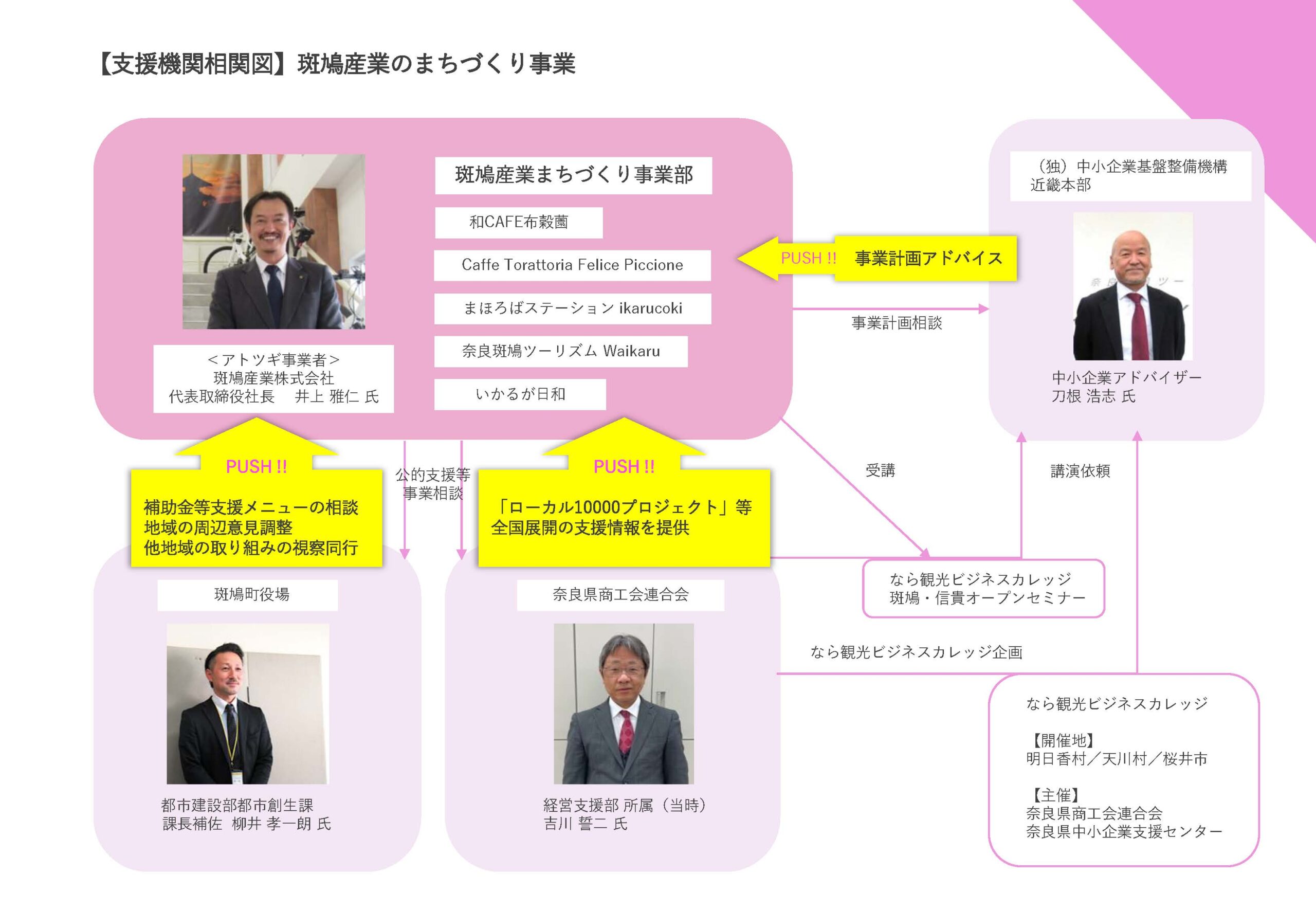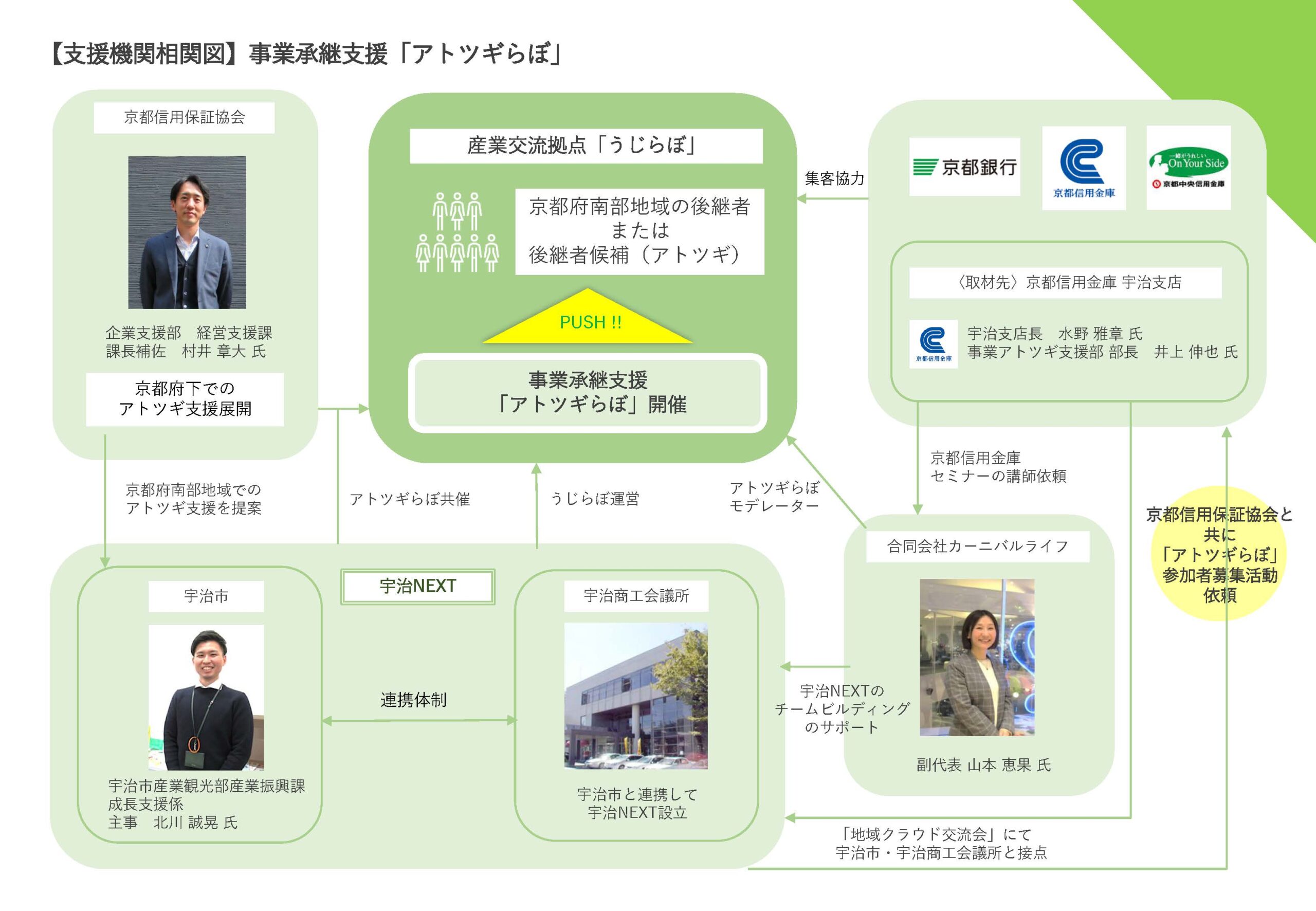2020.12.21
【インタビューvol.40】京扇子の製造卸からルームフレグランス開発へ。季節に左右されないビジネスモデルを構築したアトツギ娘の挑戦(株式会社 大西常商店 大西 里枝 氏)

夏のうだるように暑い日、着物に身を包んだ人が優雅に扇子で仰ぐ姿を見かけて、趣と清涼感を感じたことのある方は多いかもしれない。涼をとるだけでなく、七五三や婚礼などハレの日にも多くの日本人が携えてきた扇子。中でも、京都で作られる「京扇子」は、分担制で製作され、職人の手仕事による工程を87回重ねてようやく1本の扇子になる特徴がある。
そんな京扇子の製造卸を営む企業の一つが、京都・四条烏丸で昭和初期に創業された大西常商店である。取り扱う扇子の数は700種類以上。日本舞踊で使う「舞扇子」、茶道で使う「茶扇子」、和の芸術品として飾られる「飾り扇子」なども手掛ける。

大西里枝氏は、大西常商店の4代目若女将だ。2016年8月にアトツギとして家業に入り、ビジネスモデルが季節商売で不安定であることを知った大西氏。新商品の開発や新規事業の創出を行って、年間を通して安定した売上を挙げられる基盤を整えてきた。
毎日艶やかな着物に身を包み、凛々しくも優しい表情をまとって、大西常商店の“顔”といえる存在となった彼女。家業に入ってからの数々の挑戦と、その原動力を伺った。
家業の「季節商売で不安定なビジネスモデルを変えよう」と決意
Q. 大西さんは、子どもの頃から家業を継ぐことを意識していましたか?
A.実は、家業にそれほど愛着はありませんでした。とはいえ、ひとりっこなので、「最終的には私が継ぐのかな」とぼんやりと感じてはいたんです。
当社は京扇子の製造卸の会社ですが、製作は20人ほどの職人さんに依頼していて、工程を管理する統括部門のような役割を担っています。そのため、私自身、目の前で扇子が作られる様子を見る機会があったわけではなくて。だから、扇子への興味も薄かったんです。

当然、家業に興味はなかったので、大学卒業後はNTT西日本に就職して5年働きました。一時期は転勤で九州に住んでいたのですが、結婚と出産のタイミングで京都に戻ってきたんです。育休中は実家で子どもを見ていたので、家業の様子を垣間見たのもきっかけとして大きかったかもしれません。
そのときに改めて、家業のおかげで幼稚園から大学まで私学に通わせてもらえるなど、何不自由なく育ててもらったことに感謝の気持ちが湧いてきて。先代が作り守ってくれたこの商売で、私も我が子を養っていきたいと思ったんです。また、「主人にも、将来的に家業を手伝ってもらいたい」という思いはまったく無く(笑)。一方で、主人が会社員として安定していたこともあり、「主人と私、二つの柱があるから、最悪倒産したとしてもどうにか生きていけるだろう」と思えたことも勇気になりました。
Q. 家業に入るにあたって、決意されていたことはありましたか?
A.育休中に、仕事の様子を近くで見る中で、「違うやり方が考えられるのではないか」「現代の暮らしにマッチした商品づくりや新しいビジネスモデルを作るべきではないか」と思うことがあったため、それらを進めていけたらと思って家業に入りました。

家業に入って1年目、商売の流れを掴み決算書を見る中で扇子の製造卸は季節商売であることを知ったんです。当社では、4月から9月までの半年間の売上が年間売上の8割ほどを占めていて、昔は11月の七五三シーズンや結婚式に向けても扇子を製造していましたが、現代ではそのような需要も少なくなり、秋から冬にかけてはほとんど売上の無い状態でした。
また、扇子の素材自体が手に入りづらくなっていて、10月に発注した扇子の骨が翌年4月に入荷され、そこから扇子を作って8月ごろに販売するというように、現金化するまでのリードタイムが非常に長かったんです。このような背景を知って、「今のビジネスモデルでは、スケールしないし不安定だ。父の代と私の代はギリギリ維持できても、その次の代まではもたないだろう」と痛感し、変革の必要性を強く感じていました。
新商品開発や新事業の創出によって、利益率を大幅改善
Q. ビジネスモデルを変える必要があると実感されて、まず初めに取り組んだのはどういったことでしたか?
A.京扇子を扇ぐとほのかな香りがふわりと漂う、ルームフレグランス「かざ」の商品開発ですね。
ルームフレグランスは冬に需要が高まる商品であることと、扇子用に薄く加工された「扇骨」という素材に香りを保つ効果が高い点に着目しました。


商品開発にあたっては、京都商工会議所様のプログラム『あたらしきもの京都』を活用しました。京都の伝統工芸や老舗企業の商品開発を支援するプロフグラムなのですが、デザイナーさんの紹介、『東京インターナショナル・ギフトショー』への出展などでサポートしていただきました。
1年ほど掛けて開発し、2018年から販売を開始して。知名度を上げるためにクラウドファンディングなどにも挑戦しました。そこから販売数が伸びて、今では秋冬の苦しい時期の売上を支えてくれる看板商品に育っています。
Q. ルームフレグランス以外に取り組んだ新しいチャレンジはありますか?
A.それでいうと、当社の建物を、京町家レンタルスペースとして貸し出すことも始めました。
京都の街中で100坪以上の町家となると数がかなり限られるので、意外にも需要があったんです。商品撮影や舞妓さんの撮影会、コスプレイヤーの方の集いなどさまざまな用途にレンタルいただいています。

他には、春と秋のシーズンを中心に、観光客向けの投扇興(とうせんきょう※扇子を「蝶」と呼ばれる的に向かって投げ、落ちた形で点数を競う、京都の伝統的な遊び)体験の機会も提供しています。周辺の高級ホテルに営業を掛けて回り、提携を打診して、宿泊客のお客様を連れて来ていただくパッケージプランを作っていただきました。
Q. 家業に入って以降、さまざまなチャレンジを重ねられていますが、成果はどんなところで実感されていますか?
A.季節商売の扇子を支えてくれる第二の柱ができたことと、利益率が大きく改善されたことで成果を実感しています。
経常利益率は、以前は3%ほどだったのが今では10~15%になっているのですが、それはルームフレグランスや扇子の小売を始めたこと、京町家のレンタルなど、製造原価の掛からないビジネスを立ち上げたことが要因だと感じています。

新しい挑戦をするにあたって、両親から反対されたことはありません。ルームフレグランス開発時も、父はそもそもどんなものなのか理解できていなかったこともあるかも知れませんが、今のままでは事業が長く継続できないという危機感は持っていましたし、「扇子の素材を活用して、自社の利益に貢献したい」という私の一貫した思いが伝わって、止められることはなかったです。
先代が築いてくれた資産を活用して新しい挑戦ができることはアトツギの強みですし、父が社長としてどんと構えてくれているからこそ、いろんな挑戦ができているのだと思います。
「両親と先代に恩返しをしたい」気持ちが原動力
Q. アトツギとして事業を引っ張っていく中で、役立っている会社員時代の経験はありますか?
A.たとえば、属人化を無くして仕組みにしていくという視点でしょうか。家業に入った当時は、目視で在庫管理をしていて社長しかその情報を知らないという状況でした。
仕組み化と見える化の大切さは会社員時代に実感したので、在庫管理アプリで管理するフローに変えて、誰もがいつでもスマートフォンから在庫状況を確認でき、お客様やお取引先様からのご質問に即答できるようにしました。

正しく目立つことや自ら意志を伝えることの大切さも、会社員時代に学んだことかもしれませんね。同期には、自分が希望する部署への転勤が叶う確率を上げようと自分のスキルを積極的にアピールしたり、「〇〇に行きたいです」と主張したりする人もいて。私は恥ずかしくて当時はできなかったのですが、アトツギとなってからその大切さを実感しています。
だからこそ、「自分が大西常商店の広告塔になるんだ」と覚悟を決めて、お取引様やお客様、メディアの方に少しでも覚えていただくための手立てという意味でも毎日着物を着るようにしていて。クラウドファンディングなどに積極的に挑戦するのも、発信することで知っていただきたいという思いがあるからです。
Q.今後は、どんなことに取り組んでみたいですか?
A.私はシンプルに、家族の幸せのために事業をしている側面が強くて。というのも、私の原動力は、「両親、そしてこの家業を作り繋いでくれた先代に恩返しをしたい。彼らをハッピーにしたい」という思いなんです。

扇子の製造卸として自社をさらにスケールさせていくことは、これからの時代において難しいと思っていますし、私の願望としてもありません。売上高よりも経常利益を追って、年間を通して安定したビジネスモデルを築くことが一番で。だからこそ、新しいことに挑戦して事業の柱を増やしてきたんです。
ただスケールすることをめざさないだけで、今の事業以外にやりたいことはたくさんあります。そのうちの一つが、職人さんの支援です。斜陽産業である伝統産業においては、技術を持った職人さんも商売に困っており、職人の道を諦める方が多くいます。当社が扱う京扇子は、職人さんの手仕事による工程を87回重ねて、ようやく一本の扇子になります。職人さんの存在が欠かせない事業をしているからこそ、彼らが職人を続けられるための支援をしたいんです。
現在も、職人さん向けに事業計画の作り方や会計知識についてレクチャーを行い、ビジネス視点を身に付けてもらうプログラムを開催していますが、今後はさらにサポートの領域を広げていきたいと構想しています。

(文:倉本祐美加、写真:中山カナエ)
<会社情報>
京扇子 大西常商店
京都府京都市下京区本燈籠町23
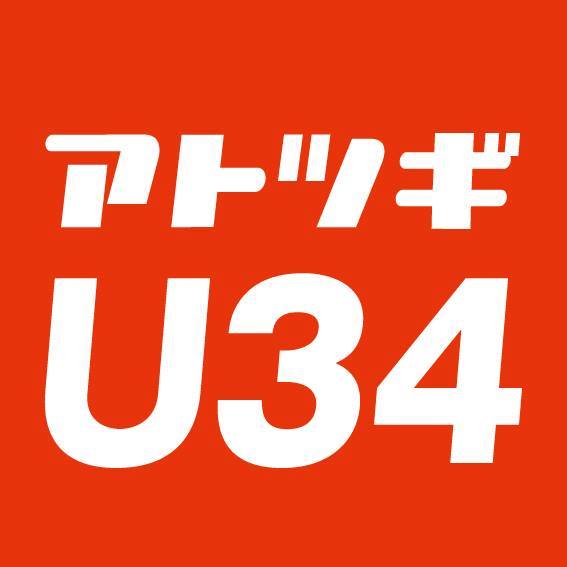
アトツギベンチャー編集部
おすすめ記事

2022.02.04
【インタビューvol.54】「違和感」は新規事業の原動力、時代の風を読んで取り組むフードロ
壷井氏は32歳で家業を継いで以降、社内外で「ただ課題解決のためだけ
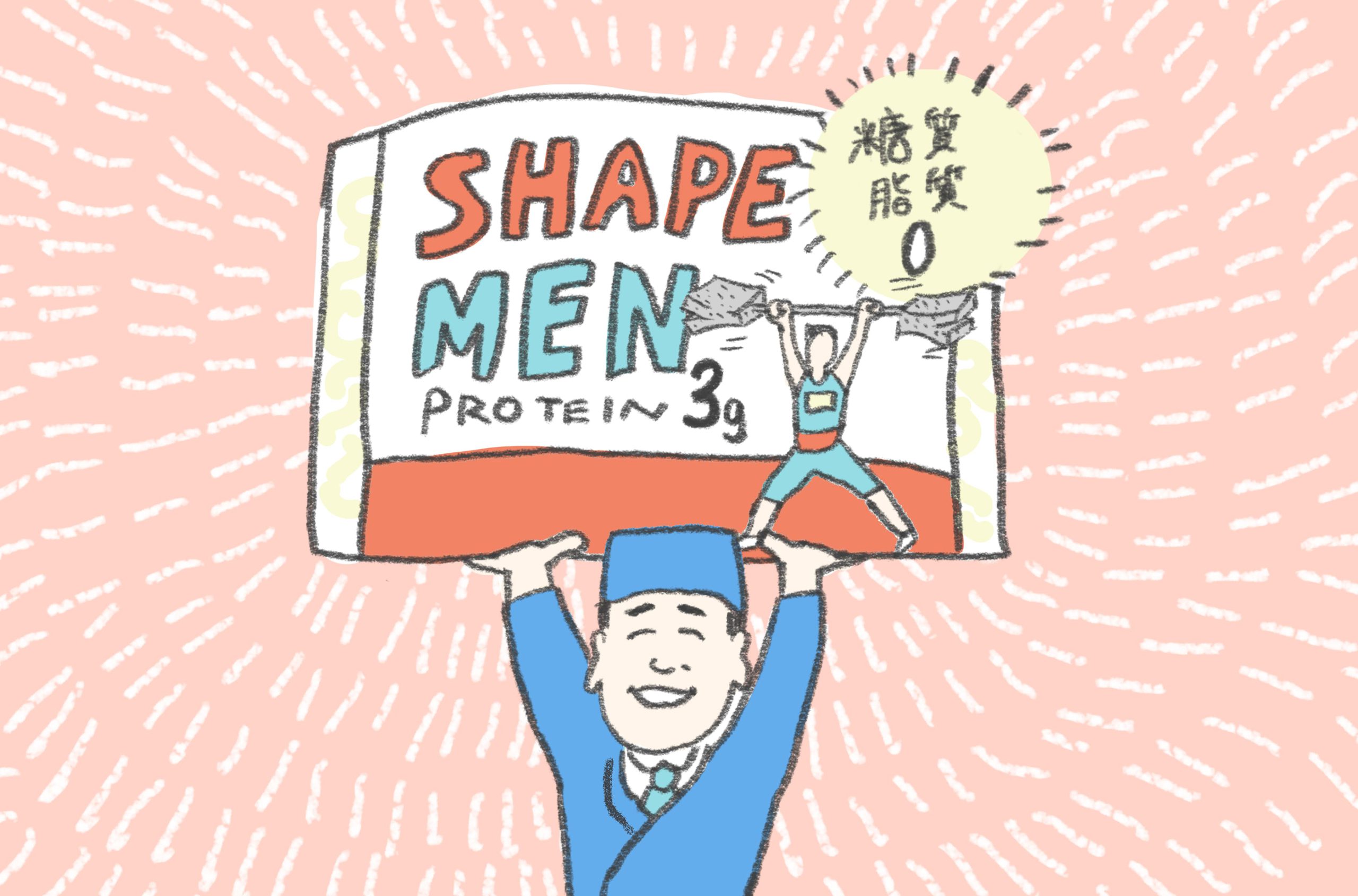
2022.01.26
【インタビューvol.53】ワールドワイドに広がれこんにゃく文化! 「SHAPE MEN」
Q. 「SHAPE MEN」って?? 一般的な「こんにゃく」とは違い、身体にじっ

2022.01.24
【インタビュー Vol.52】国内初、紙パックナチュラルウォーターで業界を革新(株式会社ハ
市販されている「水」といえば、容器は「ペットボトル」。それが当たり前だった日本で

2022.01.17
【インタビュー Vol.51】20歳で掲げた夢は「世界に必要とされる企業にする」。菓子卸売
全国に売店192店舗、食堂36店舗を展開している心幸ホールディング

2022.01.13
【インタビュー Vol.50】社員の1/3は虫博士。「個人が自立したフラットなチーム」と「
片山氏は35歳で家業を継いで以降、殺虫剤用の噴霧器メーカーから防虫資材商社へと業

2021.03.05
【アトツギピッチ優勝者インタビュー】 “船場”からテクノロジーの会社ができたらおもしろい!
2021年1月23日に開催されたアトツギピッチで優勝した株式会社志成販売の戦正典

2021.03.04
【インタビュー Vol.49】本当に美味しい生パスタを届けたい!麺一筋110余年のノウハウ
淡路島中北部の大阪湾を望む立地に本社兼工場がある淡路麺業株式会社。併設されている

2021.02.26
【インタビュー Vol.48】社長業は未来をつくる仕事。人を育てることを軸におき、家業の製
昭和11年にゴム材料商社として創業し、高度経済成長期を経て、ゴム製品を製造・販売

2021.02.24
【インタビュー Vol.47】農業×I Tで見えない技術資産を未来へつなぐ。(有限会社フク
「実は、家業に入ったきっかけはあまり前向きな理由ではなくて・・・」と苦笑しながら

2021.02.23
【インタビューvol.46】特殊曲面印刷の技術を導入する体制構築や、人材育成に注力。ライセ
福井県の特産品といえる眼鏡を販売する会社として創業した株式会社秀峰。ギフト事業参